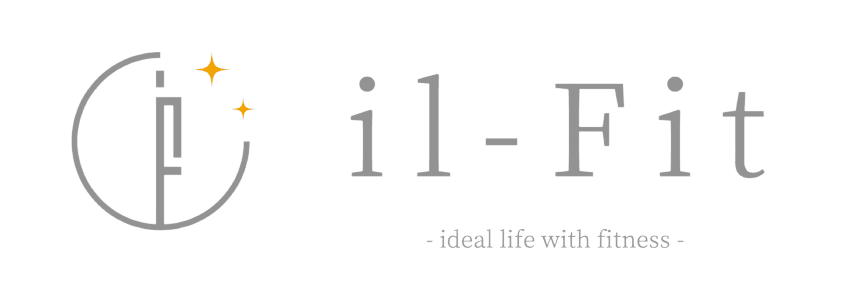スポーツの指導現場では、長年にわたり反復ドリルや「マッスルメモリー(ここでは「筋細胞核の記憶」とではなく、「反復による深く内在化された練習効果」としての意)」といった概念に基づく指導法が主流とされてきました。しかし、現代スポーツの複雑で予測不可能な状況において、これらの伝統的なアプローチだけで選手を育成することには限界が見え始めています。Renshaw et al. (2022)は、この変化しにくい指導現場の状況を「イデオロギーの惰性(ideological inertia)」と表現し、新しい科学的知見が十分に浸透していない現状に警鐘を鳴らしています。
本稿の目的は、こうした伝統的指導法の限界を乗り越えるための新しい科学的アプローチ「エコロジカル・ダイナミクス」を紹介することです。このアプローチは、選手と環境を一体のシステムとして捉え、選手の持つ適応能力を最大限に引き出すことを目指します。本稿では、その理論的背景と実践方法を、現場の指導者向けに専門的かつ分かりやすく解説していきます。
1. なぜ従来の指導法だけでは不十分なのか?
伝統的な指導法が現代のスポーツの要求に必ずしも応えられない理由を論理的に説明します。
1. 分離された練習の限界
従来の指導法では、複雑なスキルを単純な要素に分解し、それぞれを個別に練習する「分解されたドリル」が多用されます。例えば、バスケットボールにおけるディフェンスのいない状況でのシューティング練習がその典型です (Renshaw et al., 2022)。
しかし、このような練習には大きな問題点があります。それは、実際の試合状況から重要な「知覚情報」が欠落していることです。試合中、選手は相手ディフェンダーの位置、プレッシャー、味方の動きといった無数の情報に基づいて判断し、プレーを選択します。分解されたドリルではこれらの情報が完全に抜け落ちているため、練習でどれだけシュートが上手くなっても、その成果が試合でのパフォーマンスに直接結びつきにくい(転移しにくい)のです。
2. 「反復」の本当の意味
「反復練習が重要だ」という言葉は、指導現場で頻繁に使われます。しかし、その「反復」の意味を正しく理解することが不可欠です。ロシアの運動生理学者ニコライ・ベルンシュタインは、同じ動作を機械的に繰り返すこと(repetition after repetition)ではなく、「繰り返しのない反復(repetition without repetition)」の重要性を説きました (Renshaw et al., 2022)。
これは、単に同じ動きを何度も行うのではなく、多様な状況下で同じ課題を解決するプロセスを繰り返すことを意味します。例えば、毎回少しずつ異なる位置やタイミングでパスを受け、シュートを打つ練習は、選手の状況判断能力や動きの調整能力を養います。このような練習こそが、試合のあらゆる局面に対応できる真の適応能力を育むのです。
2. 新しい視点「エコロジカル・ダイナミクス」
「エコロジカル・ダイナミクス」は、スポーツにおけるスキル適応を理解するための理論的枠組みであり、生態学的心理学(Ecological Psychology)とダイナミカル・システム理論(Dynamical System Theory)を統合したアプローチです。
1. 選手と環境は一つのシステム
エコロジカル・ダイナミクスの最も基本的な考え方は、分析の単位を選手個人ではなく「選手―環境システム(performer-environment system)」として捉えることです (Davids et al., 2021; Kitagawa et al., 2022)。選手のスキルは、選手個人の能力だけで決まるのではなく、選手が置かれた環境(相手、味方、コートの状態、ルールなど)との相互作用の中で発揮されます。つまり、優れたスキルとは、選手と環境が上手く適合している状態を指すのです。
2. 理論の2つの柱
このアプローチは、J.J.ギブソンの「生態学的心理学」と、複雑な現象をシステム全体として捉える「ダイナミカルシステム理論」という2つの科学理論を統合したものです (Kitagawa et al., 2022)。これにより、選手の知覚と行動がどのように結びつき、状況に応じて動的に変化するのかを科学的に説明することが可能になります。
3. 3つの重要な概念
この選手―環境システムがどのように機能するかを理解するために、その原動力となる3つの重要な概念である「アフォーダンス」「制約」「自己組織化」を理解する必要があります。
• アフォーダンス (Affordance) アフォーダンスは、「環境が選手に提供する行為の可能性」と定義されます (Gibson, 1979)。アフォーダンスとは、選手が環境から直接的に意味を知覚するプロセスです。例えば、サッカーにおいて「ディフェンスの間にできたスペースが、ドリブルでの突破やパスをアフォードする(可能にさせる)」といったように、選手は環境の中にある「行為の可能性」を直接見つけ出し、行動に移します。指導者は、選手がより良いアフォーダンスを見つけ出せるような環境をデザインすることが求められます。
• 制約 (Constraints) 選手の動きを方向付ける要因のことです。ニューウェルの制約モデルに基づき、以下の3種類に分類されます (Kitagawa et al., 2022)。
◦ 個人的制約: 身長、体力、筋力、モチベーション、過去の経験など、選手個人に内在する要因。
◦ 環境的制約: 天候、グラウンドの状態、観客の声援、社会的な期待など、選手を取り巻く物理的・社会的な要因。
◦ 課題的制約: ルール、用具(ボールの大きさや重さ)、コートの広さ、練習の目標など、指導者が設定できる要因。 これら3つの制約は、選手の動きを制限するだけでなく、特定の動きを引き出すための「道具」となります。指導者はこれらの制約を意図的に操作することで、選手の学習をデザインすることができます。
• 自己組織化 (Self-Organization) 自己組織化は、脳からのトップダウンの指令によって動きが生まれるのではなく、上記3つの「制約」の相互作用の中で、選手が自律的に最適な動きのパターン(解決策)を見つけ出していく現象を指します (Kennedy & O’Brien, 2024)。例えば、バスケットボールの練習でコートの幅を狭める(課題的制約)と、選手は自然とドリブルの幅を小さくしたり、より縦への突破を試みたりするようになります。これはコーチが「もっと縦に攻めろ」と指示したからではなく、制約によって動きが自己組織化された結果です。
これらの概念は、指導者が選手の動きを直接修正するのではなく、選手の学習が生まれる「環境」そのものをデザインするための科学的な土台を提供します。
3. 指導者が「環境デザイナー」になるための3つの原則
エコロジカル・ダイナミクスに基づけば、コーチの役割は選手に答えを教える「指導者」から、選手が自ら答えを見つけ出すプロセスを導く「環境デザイナー」へと変わります。そのための具体的な指導原則を3つ紹介します (Kitagawa et al., 2022; Davids et al., 2012, TOSSJ-5-113)。
1. 意図の教育 (Education of Intention)
学習の第一歩は、練習課題の目標と選手の目標を一致させることです。選手が「何のためにこの練習をするのか」を明確に理解し、意図を持って取り組めるように導きます。例えば、サッカーのカウンター攻撃の練習において、単に「速く攻めよう」と指示するのではなく、「ボールを奪ってから5秒以内に相手ゴールに迫る」といった具体的な課題的制約(ルール)を設定します。これにより、選手の意図は「速く攻める」という特定の方向に導かれ、その目標を達成するためのプレーが自然と生まれます (Kitagawa et al., 2022)。
2. 注意の教育 (Education of Attention)
選手がパフォーマンス環境の中から、行為に結びつくより重要な情報源に注意を向けられるように導くプロセスです。これをアチューンメント(同調)と呼びます。例えば、クリケットの研究では、初心者の打者はボールの軌道そのものにしか注意を向けられませんが、熟練者は投手がボールをリリースする前の身体の動きといった先行情報に注意を向け、次に何が起こるかを予測します (Kitagawa et al., 2022; Renshaw et al., 2022)。指導者は、選手がどこに注意を向けるべきかを直接教えるのではなく、重要な情報が含まれる状況を練習の中に作り出すことで、選手が自ら注意を向けるべき情報源に同調していくプロセスをサポートします。
3. 較正の教育 (Education of Calibration)
選手は、疲労や成長、用具の使用などによって常に自身の行為可能性(何ができるか)が変化します。その変化に合わせて、知覚した情報と実際の動きを調整していくプロセスがキャリブレーション(較正)です。例えば、走り幅跳びの選手は、助走中に自分のスピードや歩幅から「このままだと踏み切り板をオーバーしてしまう」と知覚し、無意識のうちに最後数歩のストライドを微調整します (Renshaw et al., 2022)。このような自己調整能力は、多様な状況を経験することで磨かれます。指導者は、選手の身体や能力の変化を考慮し、常にキャリブレーションが求められるような練習環境を提供することが重要です。
これら3つの原則は、それぞれが独立しているのではなく、深く相互に関連した一つのサイクルを形成しています。明確に定義された意図(例:「5秒以内にゴールに迫る」)は、選手の注意を特定の情報(例:ディフェンスの隙間)へと自然に向けさせます。そして、その情報に基づいて行動するには、変化し続ける身体の状態や動的な環境に合わせて、常に動きを較正していく必要があります。指導者にとって、これはデザイン、観察、そして改善を繰り返す、継続的なプロセスなのです。
4. 理論から実践へ:練習デザインの具体例
エコロジカル・ダイナミクスの理論を実際の練習デザインに落とし込むにはどうすれば良いのでしょうか。
1. 良い練習の鍵:「試合状況の再現性」
良い練習デザインの鍵は、代表性のある学習デザイン (Representative Learning Design)、つまり練習が「本番のように見え、感じられるか」にあります (Renshaw et al., 2022)。練習で得たスキルを試合で発揮させるためには、練習環境が試合環境を忠実に再現している必要があります。
• クリケットの事例: オーストラリアのチームがインドで試合をする際、現地の気候やボールが弾みやすいピッチの特性を再現した練習環境を特別に作り、選手を適応させました。
• 走り幅跳びの事例: 単に跳ぶ練習を繰り返すのではなく、「予選最終跳躍で、トップ8に残るにはこの距離が必要」といった試合の特定の局面を模した「ビネット(vignette)」と呼ばれる練習を行い、プレッシャー下での自己調整能力を高めました。
これらの事例は、練習に試合と同じ制約(情報)を組み込むことで、スキルの転移がいかに高まるかを示しています。
2. 改善すべき練習の例:バスケットボールのシューティング
• 問題点: 相手ディフェンダーがいない状況での反復練習は、試合でシュートを成功させるために最も重要な「ディフェンダーのプレッシャー」という制約が欠けています。そのため、練習での高い成功率が試合でのパフォーマンスに繋がりにくいという問題があります (Renshaw et al., 2022)。
• 改善策: 練習にディフェンダーという課題的制約を一つ加えるだけで、練習の質は劇的に変わります。選手は、ディフェンダーの動きという新たな情報に対応するため、シュートを打つタイミングやフォーム、リリースポイントなどを自律的に調整し始めます。コーチが細かく指示しなくても、選手は状況に適応しようと動きを変化させるのです。これにより、より実践的で適応的なシュートスキルが生まれます (Gorman & Maloney, 2016)。
5. 指導者の役割
このアプローチは単純な万能薬ではありません。指導者は、これまでの指導観を大きく変える必要があり、現場では様々な現実的な課題に直面することが予測されます (Kennedy & O’Brien, 2024)。
1. 指導者に投げかけられる問い
このアプローチを実践する上で、指導者は以下のような問いと向き合うことになります。
• 選手の「エラー」をどう捉えるか? それは修正すべき「間違い」なのか、それとも最適な動きを探す適応過程における機能的な「ゆらぎ」なのか?
• 意図しない動き(いわゆる「悪い癖」)が定着してしまった場合、指導者はいつ、どのように介入すべきか? 直接的な修正を避けるべきだとしても、放置してよいのか?
• 経験の浅い指導者は、どの「制約」を、どの程度、いつ変更すれば良いかを、試行錯誤以外にどう学んでいけば良いのか?
2. 指導者の新たな役割
これらの問いに唯一の正解はありません。重要なのは、指導者の役割が「答えを与える者」から「選手の探求と自己発見を促す学習環境を巧みにデザインする者」へと変化することを認識することです。選手のエラーを学びの機会と捉え、選手の自律的な探求を辛抱強く見守り、制約の操作を通じてそっと導く。それが、エコロジカル・ダイナミクスに基づく新時代の指導者像です。
結論
エコロジカル・ダイナミクスに基づく指導法の要点は、以下の2つのポイントに集約されます。
1. 指導の焦点は、理想的な「型」を教え込むことから、選手の適応的な動きが自然に生まれる「環境」をデザインすることへ移行する。
2. 学習とパフォーマンスは別々のイベントではなく、選手が環境に絶えず適応していく、絡み合った一つのプロセスである。
この新しい視点を取り入れることは、時に忍耐を要するかもしれません。しかし、選手の自律性と適応能力を信じ、その可能性を真に引き出すための鍵となるアプローチであることは間違いないでしょう。
引用・参考文献
• Davids, K., Araújo, D., Hristovski, R., Passos, P., & Chow, J. Y. (2012). Ecological dynamics and motor learning design in sport. In Skill acquisition in sport: Research, theory and practice (pp. 112-130). Routledge.
• Gorman, A. D., & Maloney, M. A. (2016). Representative design: Does the addition of a defender change the execution of a basketball shot? Psychology of Sport & Exercise, 27, 112–119.
• Kennedy, A., & O’Brien, K. A. (2024). Adding texture to the Art of constraints-led coaching: a request for more research-informed guidelines. Sports Coaching Review, 1-18.
• Kitagawa, S., Kuramoto, K., & Uwaizumi, K. (2022). A Philosophical Study on Ecological Training: Proposing a New Training Conception of Ball Game of Team Sports. Journal of Health, Sport and Kinesiology, 27, 1–15.
• Renshaw, I., Davids, K., O’Sullivan, M., Maloney, M. A., Crowther, R., & McCosker, C. (2022). An ecological dynamics approach to motor learning in practice: Reframing the learning and performing relationship in high performance sport. Asian Journal of Sport and Exercise Psychology, 2(1), 18–26.
• 伊藤 万利子. (2015). エコロジカル・アプローチによる熟達化研究:わざの成立を支える知覚的制御. 博士論文, 東京大学大学院.