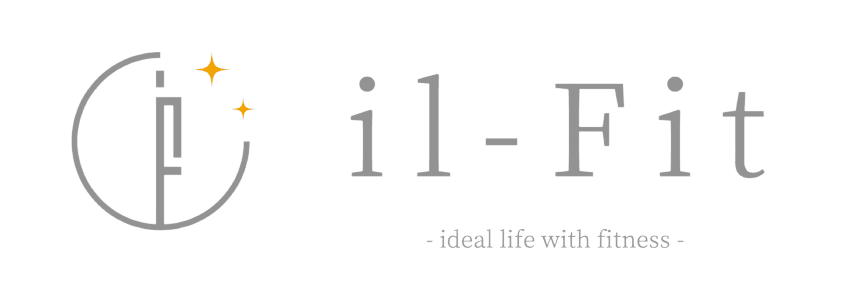筋肉と脳は、一見すると全く異なる機能を持つ臓器のように思われます。筋肉は身体を動かし、脳は思考や記憶を司る。しかし、近年の研究により、この二つの臓器は想像以上に密接な関係にあることが明らかになってきました。
今回は下記の論文を紹介します。
紹介論文
Brisendine MH, Drake JC. Integrative physiology of skeletal muscle for maintaining cognitive health. The Journal of Physiology. 2025. doi:10.1113/jp286748.
この論文が注目される背景には、世界的な高齢化社会の進展があります。認知機能の低下やアルツハイマー病などの神経変性疾患は、個人の生活の質を大きく左下させるだけでなく、社会全体にとっても深刻な課題となっています。
従来、認知機能の維持は「脳中心」のアプローチで考えられてきましたが、本論文は骨格筋という末梢組織が認知機能に与える影響の重要性を示しています。
Contents
研究の背景と目的
これまでの医学では、認知症やアルツハイマー病は主に脳の問題として捉えられてきました。アミロイドβプラークの蓄積、神経原線維変化、脳萎縮といった脳内の病理変化が注目の中心でした。
しかし、近年の研究により、認知機能低下の前兆として末梢システム、特に骨格筋の変化が観察されることが報告されています。例えば、握力の低下や歩行速度の減少といった身体機能の変化が、認知症の診断よりも数年早く現れることが知られています。
本論文の著者らは、骨格筋が単なる運動器官ではなく、内分泌器官として脳に影響を与える「マイオカイン」と呼ばれる生理活性物質を分泌していることを強調しています。さらに、末梢運動神経や神経筋接合部の機能変化が、認知機能低下の早期指標となる可能性を提示しています。
筋肉量・筋力低下と認知症リスクの関連
サルコペニアとダイナペニア:認知症の前兆?
論文では、筋肉量の減少(サルコペニア)と筋力の低下(ダイナペニア)が認知症発症と強く関連していることを詳述しています。
通常の加齢過程では、中年期以降に筋肉量が年間約1%ずつ減少し、70代後半から80代前半までに最大50%の筋肉量が失われます。しかし、アルツハイマー病の前臨床期においては、この筋肉量減少が加速することが複数の研究で示されています。
特に注目すべきは、筋肉量や筋力の低下が軽度認知障害(MCI)やアルツハイマー病の診断よりも数年早く現れることです。握力測定という簡便な検査で評価できる筋力低下が、将来の認知機能低下を予測する指標となる可能性があります。
性差の影響
論文では、サルコペニアとダイナペニアの進行に性差があることも指摘されています。閉経後の女性は男性よりも急速な筋肉量減少を経験し、これがアルツハイマー病のリスク上昇に寄与している可能性があります。女性がアルツハイマー病に罹患しやすい理由の一部は、この筋肉量減少の性差によって説明されるかもしれません。
マイオカイン:筋肉から脳への化学的なメッセージ
BDNF(脳由来神経栄養因子)の重要性
骨格筋が内分泌器官として機能する最も重要な例が、BDNF(Brain-Derived Neurotrophic Factor)の分泌です。BDNFは神経細胞の成長、分化、生存を促進する蛋白質で、学習や記憶の形成に重要な役割を果たしています。
運動により骨格筋ではproBDNF(BDNF前駆体)の発現が増加し、これが切断されて活性型BDNFとして血中に放出されます。この運動後のBDNF上昇は24時間持続することが報告されており、運動の認知機能改善効果の重要なメカニズムの一つと考えられています。
アルツハイマー病では脳内のBDNF濃度が低下していることが知られており、筋肉由来のBDNFがこの不足を補完する可能性があります。実際に、マウス実験では筋肉特異的にBDNF関連遺伝子を過剰発現させることで、アルツハイマー病モデルマウスの認知機能が改善することが示されています。
その他の重要なマイオカイン
カテプシンB: 運動により筋肉から分泌され、脳内でのBDNF発現を促進します。カテプシンB欠損マウスでは運動による脳内BDNF上昇が阻害されることから、運動効果の仲介役として重要です。
イリシン: FNDC5というタンパク質から切り出されて分泌されるマイオカインで、運動による認知機能改善に必須の因子とされています。イリシンも脳内でのBDNF発現を促進する作用があります。
プロサポシン(PSAP): 神経細胞のリソソーム機能を促進する神経栄養因子で、運動により筋肉から分泌されます。PSAP類似体をアルツハイマー病モデルマウスに投与すると、BDNF発現とシナプスマーカーの発現が増加し、シナプス再編成が促進されます。
神経筋接合部:脳と筋肉をつなぐ重要な接点
神経筋接合部の構造と機能
神経筋接合部(NMJ:Neuromuscular Junction)は、運動神経と骨格筋が接続する部位で、脳からの運動指令を筋肉に伝達する重要な構造です。NMJは前シナプス(運動神経終末)、シナプス間隙(シナプス基底膜)、後シナプス(筋線維と筋膜)の三つの要素から構成されています。
アルツハイマー病におけるNMJ機能障害
論文では、アルツハイマー病においてNMJ機能障害が早期から現れることを詳述しています。人間を対象とした研究では、下肢の末梢神経機能障害が認知症発症リスクを約2倍に上昇させることが16年間の追跡調査で明らかになっています。
アルツハイマー病マウスモデルを用いた研究では、認知機能低下に先行してNMJの形態的・機能的異常が観察されます。例えば:
- Tg2576マウス(アミロイドβ蓄積モデル)では、神経長の短縮、前シナプス面積の減少、コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)の減少が観察されます
- 3xTgADマウス(APP、Tau、プレセニリン変異)では、NMJの断片化と脱神経、坐骨神経刺激による筋収縮力の低下が見られます
- 5xFADマウスでは、認知機能低下に先行して神経刺激による筋トルク産生の障害が発生します
APP(アミロイド前駆体タンパク質)の役割
アルツハイマー病の病理学的特徴であるアミロイドβプラークの原料となるAPPは、実はNMJにも高発現しています。APP及びその関連タンパク質(APLP1、APLP2)は、NMJの安定性と信号伝達に重要な役割を果たしています。
興味深いことに、筋肉特異的に変異APPを過剰発現させたマウスでは、海馬での神経新生が減少し、うつ様行動が観察されます。これは筋肉からのBDNF分泌減少や海馬での細胞老化促進によるものと考えられており、筋肉の病理変化が直接的に脳機能に影響を与えることを示す重要な知見です。
ミトコンドリア機能とAMPKシグナルの複雑さ
ミトコンドリアの重要性
ミトコンドリアは細胞のエネルギー産生を担う細胞小器官で、神経細胞と筋細胞の両方でエネルギー需要が高いため、豊富に存在しています。ボルチモア老化縦断研究では、骨格筋ミトコンドリア呼吸能の低下が認知機能障害を予測し、アルツハイマー病のバイオマーカー(p-tau181、神経フィラメント軽鎖、アミロイドβ42/40比など)と相関することが示されています。
逆に、高い骨格筋ミトコンドリア機能を有する個体では、認知機能に関連する脳領域の構造的完全性が保たれていることも報告されています。
AMPK(AMP活性化プロテインキナーゼ)の二面性
AMPKは細胞のエネルギーセンサーとして機能し、ミトコンドリアの品質管理(生合成と除去の両方)を調節する重要な酵素です。筋肉においては、AMPK活性化が運動によるNMJ関連遺伝子の発現増加やアセチルコリン受容体のクラスタリング促進に寄与します。
しかし、論文では神経系におけるAMPKの複雑な役割についても言及しています。軸索においては、AMPK活性の増加がミトコンドリアの逆行性輸送を阻害し、損傷したミトコンドリアのシナプスからの除去を妨げる可能性があります。実際に、アルツハイマー病の脳やマウスモデルでは神経細胞のAMPK活性が異常に上昇しており、これがシナプス機能障害に寄与している可能性があります。
さらに、アルツハイマー病脳では通常優位であるAMPKα2サブユニットに対してAMPKα1サブユニットの相対的発現が増加しており、これがエネルギーストレスに対する応答性を変化させている可能性があります。
この組織特異的なAMPK機能の違いは、治療戦略を考える上で重要な課題となります。筋肉ではAMPK活性化が有益である一方、脳神経系では過度なAMPK活性化が有害となる可能性があり、システム全体を考慮したアプローチが必要です。
臨床的・社会的意義
運動介入の可能性
論文の知見は、運動介入の重要性を科学的に裏付けています。運動による筋肉収縮は:
- マイオカイン(BDNF、イリシン、カテプシンBなど)の分泌を促進
- ミトコンドリア機能を改善
- NMJ機能を維持・改善
- 結果として認知機能を保護
ただし、論文では運動介入の効果が神経変性疾患の進行段階や個体差によって異なる可能性も指摘しており、より個別化された運動プログラムの開発が必要としています。
既存薬剤の新たな可能性
アルツハイマー病治療薬として承認されているドネペジル(アセチルコリンエステラーゼ阻害薬)について、論文では興味深い知見を紹介しています:
- 軽度アルツハイマー病患者でドネペジル投与により歩行速度が改善
- 単離骨格筋でドネペジル処理により強縮トルク産生と終板電位持続時間が増加
- 軽度認知障害患者でドネペジルが骨格筋ミトコンドリア機能を正常化
これらの知見は、既存の認知症治療薬が脳だけでなく末梢神経筋系にも作用することを示しており、多面的な治療効果の可能性を示唆しています。
早期診断・予防戦略への展望
筋力測定やNMJ機能評価が認知機能低下の早期指標となる可能性は、予防医学の観点から極めて重要です。握力測定のような簡便な検査で将来の認知症リスクを予測できれば、より早期からの介入が可能になります。
また、骨格筋ミトコンドリア機能の評価が認知症のバイオマーカーとして活用できる可能性もあり、侵襲的な脳脊髄液検査や高価なPET検査に代わる、よりアクセシブルな評価法として期待されます。
まとめ
本論文は、認知機能の維持が単純な「脳の問題」ではなく、骨格筋、末梢神経、そして脳を含む統合的なシステムの問題であることを明確に示しています。
主要な知見をまとめると:
- 筋肉量・筋力低下は認知症の前兆: サルコペニアとダイナペニアが認知症診断に先行して現れる
- 筋肉は内分泌器官: BDNF、イリシン、カテプシンB、プロサポシンなどのマイオカインを分泌し、脳機能を調節
- 神経筋接合部は重要な指標: NMJ機能障害が認知機能低下の早期バイオマーカーとなる可能性
- ミトコンドリア機能の重要性: 骨格筋ミトコンドリア呼吸能が認知機能を予測
- AMPKの組織特異的機能: 筋肉では有益だが、神経系では過活性化が有害となる複雑性
これらの知見は、従来の「脳中心主義」から「システム統合主義」への視点転換を促しています。認知症予防・治療においては、脳に加えて筋肉と末梢神経系の健康維持が重要であり、運動介入や既存薬剤の多面的効果を活用した包括的アプローチが求められます。
感想
この論文を読んで最も印象的だったのは、筋肉を単なる「身体を動かす器官」から「脳との対話装置」として捉え直す視点の転換です。筋肉が収縮するたびに様々な生理活性物質を分泌し、それが血流を通じて脳に届いて神経保護効果を発揮するという仕組みは、まさに身体の「化学的通信ネットワーク」と呼ぶにふさわしいものです。
特に興味深いのは、運動の認知機能改善効果が単純な「血流改善」や「酸素供給増加」といった古典的説明を超えて、分子レベルでのメカニズムが解明されてきていることです。BDNFやイリシンといったマイオカインの発見は、なぜ運動が「脳に良い」のかを科学的に説明する重要な手がかりとなっています。
一方で、AMPKの組織特異的な機能差については、生物学の複雑さを改めて感じさせられます。同一の分子経路が組織によって正反対の効果を示すという事実は、システムの複雑性を物語っています。将来的な治療戦略では、この組織特異性を考慮した精密医療的アプローチが必要になるでしょう。
この研究は、日常的な筋力トレーニングや有酸素運動の意義を再考させてくれます。単に筋肉を鍛えるだけでなく、同時に脳を保護し、将来の認知症リスクを軽減している可能性があるのです。特に中年期以降の運動習慣は、筋肉量維持だけでなく認知機能維持の観点からも極めて重要と言えるでしょう。
今後の研究課題としては、個人差の大きい運動効果をどのように標準化し、最適化していくかが挙げられます。遺伝的背景、性別、年齢、疾患ステージなどを考慮した個別化運動プログラムの開発が求められるでしょう。
また、この知見をどのように臨床実践に反映させるかも重要な課題です。握力測定やNMJ機能評価を認知症スクリーニングに組み込むための標準化された手法の確立、筋肉量・筋力維持を目的とした介入プログラムの社会実装などが必要になります。
最後に、この研究は「健康的な老化」というコンセプトに新たな視点を提供してくれます。脳の健康と身体の健康は不可分であり、統合的なアプローチによってこそ真の健康長寿が実現される。そんなメッセージを込めた重要な研究として、今後の発展に大いに期待したいと思います。